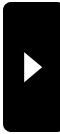2010年11月16日
薪ストーブの再生③
薪ストーブの製作関連の回顧録の続きです。
まだ使い始めでステンレスがピカピカしてますねェ
ステンレスは少々お高いのですが、耐久性を考えてチョイスしました。
ただ、薄っぺら板なので、熱で湾曲しますし、錆びにくい程度のものです。

排煙装置に煙突をくぐらせた画像です。
まだ使い始めでステンレスがピカピカしてますねェ
ステンレスは少々お高いのですが、耐久性を考えてチョイスしました。
ただ、薄っぺら板なので、熱で湾曲しますし、錆びにくい程度のものです。

排煙装置に煙突をくぐらせた画像です。

(↑)遮熱材を巻きつけたところです。
この遮熱材は北海道ではホームセンターなどに一般的に販売されているもので,
当時使用したものは,50cm程度の長さで2000円位でした。
ただ、パッケージングには、薪ストーブなど熱くなる煙突には巻かないように
してくだいとの但し書がありました。確かに激しい燃焼時に直巻きすると、
焦げが生じます。ココは要対策です。

(↑)煙突が予想以上に長くなったので,
ペグ(ソリステ)に針金を通して支えの補強をしました。
煙突はかなりの長さになるので,パイルドライバーを煙突を挟むように
2本差しにして針金で固定しています。
テントのすそは風でばたついて煙突に触れないようにしっかり地面に固定
しました。

煙突部の横部です。こうしてみると結構長いものです。
ストーブから立て板まで1mくらいの距離をとっています。これで、
縦の煙突の高さを2倍とる計算をすると,リビングシェルと同等、
またはそれ以上の高さが必要になってきます。
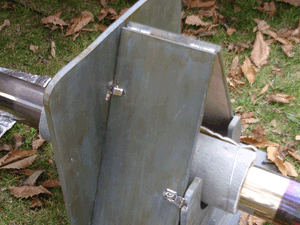
木肌がそのままでると味気ないのでにテント色に合わせて
グレーに着色しました。雨にも当たる部分ですので,ニスを塗り防水性を
高める役目もかねて。

小川のチビストーブに比べ、本体が大きく煙突の数も多いため、大げさなケースに
なりました。(これも持ち出しにくい要因
 )
)
実際の使用感ですが、暖まり方は暖房機よりもずっと早いです。
特にランステやパビリオンなどの大きな幕体だと、これくらいの熱量でないと
ダメですね。
ガンガンくべたら,ステンレスが赤々と色を変えてキツネ色になって燃えます。
上画像にあるように、このストーブは脚が短いので,当時は芝の焦げ防止に
本来壁などに当てる遮熱シートを2枚重ねにして下に敷いていました。
裏技として,*焚火台Lのベースプレートがやや小さめですが流用できます。
また、ユニフレームのクーラーBOXスタンドの上にストーブを置いて高さを
かせぐのもいいアイデアです。
地面と適度な距離ができ,かつ、ストーブも高くなって使い勝手がよくなります。
それでも、芝を痛める熱量があります。
予断ですが、スノーピークからアナウンスされた秋の新商品にこんなものがありますね。
今までベースプレートを置いて芝を痛めた記憶はないんですが、やりすぎる人が
少なからずいるから、*も商品化対策をしなければならないんでしょう

これも使えますね。
北海道の場合、冬キャンは間違いなく雪上キャンプなので、しっかり熱対策しないと
ストーブの下だけ雪が解けて水浸しなんてことになるのかな?
雪上での投入は未経験なので今冬にレポートできればと思っています。
これから薪ストーブ導入をお考えの方に・・・
火入れでは最初から薪を入れすぎないこと。
薪の太さにもよりますが,始めに入れる時は,4~5本程度で様子をみましょう。
煙の逃げなどがきちんと確認できたら,2本程度を時間をおきながら,足していきます。
入れすぎサインとしては,ストーブが赤々となる状態になります。
そうなったら,よろしくない状態
 なので燃え収まるまで時間をおきましょう。
なので燃え収まるまで時間をおきましょう。煙突周りもかなりの熱さですので、お子さんには十分注意を。
もちろん
 ストーブは煙突を短くして、屋外に持ち出しても使えますよ
ストーブは煙突を短くして、屋外に持ち出しても使えますよ
暖房、湯沸かし、鍋かけ・・・など一台三役以上の働きです。

こうして回顧録を書いていると、当時の苦心が思い出されます。
昔は熱心にやっていたものです

今回はクーラーBOXスタンド使用を前提で考えていますが
「あるもので何とかしよう思考」が年々強くなっていますので(笑)
何も作らないで終わるかもしれません

とりあえず、ストーブをケースからださなくちゃ

次回はストーブつながりで、『石油ストーブをキャンプで使う』 編の予定。
これにて、薪ストーブ編は一旦、終了します。
【追記】2011年10月13日
その後*ランドステーションLにて薪ストーブを
少し手直しして、再インストールしてみました。
興味のある方はこちらをご覧ください。
タグ :薪ストーブ
Posted by ezo at 12:01│Comments(0)
│薪ストーブ